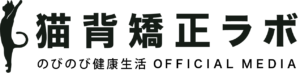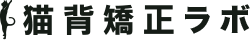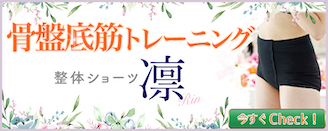コロナ禍において、生活様式が一変しました。これにより体の変化も出てきた方もいらっしゃると思います。
整骨院や整体院を経営していると、「最近こんな患者様が多いなあ」ということに気づくことがあります。
特に昨年から今年にかけて例年より多いと感じるものは、肩こり、首の痛み、頭痛など比較的上半身のものです。
その元をたどっていくと、ある一つのキーワードが浮かびました。
それは「コロナ首」というものです。文字通り「コロナ禍において、生活様式の変化における首などの痛み」によるものです。
この「コロナ首」放っておくといろいろ危険があるので、この場で警笛を鳴らしつつ、
- 「コロナ首」とはどんな状態なのか
- 「コロナ首」の原因とは
- 「コロナ首」の症状
- 「コロナ首」の解消方法
- 「コロナ首」を解消する3つのストレッチ
についてご紹介します。
「コロナ首」とは
「コロナ首」とは、「コロナ禍において、生活様式の変化における首などの痛み」の総称です。
「コロナ首」には様々な症状もありますが、この症状を引き起こす原因となるのは姿勢です。
「コロナ首」の姿勢的な特徴は?

「コロナ首」になる方の共通点として、姿勢があります。
それは「顔が前に突き出してしまう」というものです。
特にテレワークにおいて、体育すわりで行なう方がいらっしゃいますが、重心とのバランスを取るために、顔を前に突き出してしまうケースがあるのです。
「コロナ首」とストレートネックとの違いは?
「コロナ首」とストレートネックと何が違うのでしょうか?
端的にお伝えすると、「コロナ首」は「ストレートネック+あごが上がった状態」です。
ストレートネックになると、人によっては首が前傾姿勢になります。その状態が強くなるとあごが上がってくるのです。
「コロナ首」の原因とは
「コロナ首」の原因として考えられるものを以下に挙げさせていただきました。
いつもと違う姿勢での在宅ワーク
会社ではご自身のデスクがありました。
その姿勢でデスクワークするのに慣れていたと思います。
しかし在宅ワークにおいての環境整備がなされていない方もいらっしゃいます。
特にローテーブルなどを用いて、床座りにてパソコンを操作する場合、良い姿勢がキープするのが難しいものです。
結果バランスを取るために、顔を前に突き出した状態になってしまうケースが多いのです。
不自然な姿勢によるスマホ時間の増加

自宅にいることが多くなると、自然とスマホ時間が多くなるようです。
ロート製薬が2020年6月に「コロナ禍の暮らしの変化に関する調査」をしておりますが、その結果によると、在宅勤務の方のうち、22%の方のデジタル接触時間が1日あたり5時間以上も増えたそうです。
出典:ロート製薬:コロナ禍における、デジタル接触時間は+5時間にも。目を酷使する人が増加し、お悩みも深刻に。
自宅でのデジタル接触時間が増えたことで、ダイニングテーブルだけでなく、ソファに座りながら、ベッドに横たわりながらといった、スマホ姿勢が崩れていると予測されます。
巣ごもり生活によるストレス
ストレスというものは重なってくると、体にも支障が出てくることが知られています。
特に腰痛な肩こり、頭痛などが代表例です。
外出できないというストレスの代償は大きく、この痛みやコリが首に出ているのだと想像するに難くないでしょう。
マスク生活での影響
「マスク頭痛」に代表されるように、マスク生活は体にも悪影響を及ぼしています。
その中でマスクをすることであごが上がりやすい傾向があると感じています。
その理由として、マスクにより鼻呼吸より口呼吸の割合が大きくなると仮説を立てています。
特にマスクをつけることにより、呼吸に制限が加わることで、よりたくさんの空気を吸おうと口呼吸になりがちです。
口呼吸をすることで、あごが上がりやすくなるのです。
「コロナ首」の症状とは?
「コロナ首」の代表的な症状についてご紹介します。
首の痛み・コリ
「コロナ首」と言われるだけあって、やはり首の痛みやコリが中心になります。
特に出やすいのは、首の後面の重だるさとコリです。
「コロナ首」の姿勢を2つ紹介すると、「顔が前に突き出した状態」「ストレートネック+あごが上がった状態」です。
顔が前に突き出すと、首の後部にある頭半棘筋という筋肉が引き伸ばされて疲労を起こします。
あごが上がると、後頭部と首の境目部分が詰まります。
よってこの2つの部分が凝り固まってくるのです。
後述しますが、後頭部と首の境目が凝り固まると、後頭部付近の頭痛や重だるさの原因となります。
肩こり
「コロナ首」では顔が前に突き出すので、肩こりの原因となる肩甲挙筋が過度に働きます。
在宅ワークやスマホ時間では、この状態が長くなるものですから、肩こりが慢性化するのは時間の問題なのです。
頭痛
「コロナ首」における頭痛は、後頭部に出るものと、側頭部(偏頭痛)と2つのパターンがあります。
後頭部に出る頭痛
後頭部に出る頭痛は、前述の首の痛み・こりの延長線として出現することが多いです。
特に「顔を前に突き出した姿勢」を取っていると、頭半棘筋が緊張してきます。
頭半棘筋は後頭部にある後頭筋と筋膜上つながっていますから、必然と後頭部が凝り固まってきます。
この部分がコリから重さに変わり、そして痛みに変化してくるのです。
側頭部に出る頭痛
このコロナ禍でマスク生活を余儀なくされました。
マスクをすることで酸欠になる、よってあごが上がってくる方がいらっしゃると思います。
また同時にゴムにいつもテンションがかかり筋肉に負担がかかる、その結果「マスク頭痛」が生じるということは、よく聞かれます。
これに加えて、「口の筋肉の動きを阻害される」ことも頭痛の原因になりえます。
マスクをすることで口が抑えられるため、口の大きな筋肉である咀嚼筋の働きが制限されます。
咀嚼筋で代表的な筋肉は、頰にある咬筋と、側頭部にある側頭筋です。
側頭部の頭痛は、たいてい側頭筋の硬直によるものなのですが、マスク生活により側頭筋が硬くなりやすいのです。
「コロナ首」はどう解消すればいいのか?
これまでで「コロナ首」の原因や症状など、ご理解いただいたと思います。
ではどうやってこの「コロナ首」を解消すればいいのか、ご紹介します。
「コロナ首」の症状を解消する
痛みやコリは今すぐにでも解消したいものです。
この痛みは、筋肉性のものなら筋肉がほぐれれば緩和します。
よってストレッチをしたり、自分で押したりすることで、スーッとすることもあります。
ただあまりにも強い痛みだったり、なかなか取れない場合は、整形外科や脳神経外科、整骨院などで診てもらいましょう。
「コロナ首」の姿勢から改善する
そして何より重要なのは「コロナ首」の原因となっている姿勢を改善することです。
「コロナ首」特有の姿勢、「顔を前に突き出している状態」「ストレートネック+あごが上がった状態」は、筋肉に負担をかけます。
よってこの姿勢を改善することが急務なのです。
「コロナ首」に効果的なストレッチを3つ紹介
それでは「コロナ首」の解消に有効なストレッチを3つ紹介します。
顔引っ込め
何度も繰り返しますが、「コロナ首」の特徴的な姿勢は、「顔を前に突き出している状態」です。
よって顔を前に突き出した状態から、「体の上に頭を綺麗にのせた状態」を作っていく必要があるのです。
1.思いっきり顔を前に突き出します

2.ゆっくり10秒かけて、突き出した顔を元に戻します

このストレッチの2つのポイントとして、①より正しい頭の位置で筋肉をストレッチさせること ②その姿勢を感覚的に覚えさせること があります。
はじめは2の姿勢に違和感がありますが、毎日続けると体が慣れてきます。
ねこ首ストレッチ
「顔が前に突き出してしまう状態」の原因として、ねこ背が挙げられます。
特に背骨の上の方(上部胸椎)が丸まると、顔が自然と前に出てしまうのです。
よってこの「ねこ首ストレッチ」では、上部胸椎の動きをつけて、自然と頭がのる姿勢を作り上げることを目的としております。
1.まず普通に正しい姿勢を作ります

2.目線をできるだけ後ろの方に持っていくイメージで、首を後ろに倒します

※注意として、下の写真のように、首だけで曲げないこと。

首押しポーズ
「コロナ首」で症状が出るであろう部分を、直接押すという方法です。
症状の緩和だけでなく、頭の位置の改善にも役立ちます。
1.親指を除いた4本の指でわしづかみにするイメージで、首のコリに当てます

2.そのまま4本の指に力を入れて押していきます(10秒間)
反対側も手を持ち替えて同様に行なっていきます

まとめ
「コロナ首」とは、「コロナ禍において、生活様式の変化における首などの痛み」の総称です。
姿勢的な特徴として「顔を前に突き出した状態」になります。
またストレートネックに似ていますが、その違いは「コロナ首」の場合「ストレートネック+あごが上がった状態」だということです。
コロナ禍で在宅勤務やマスク生活など姿勢が崩れるケースが多くなりました。またこれに加えて巣ごもりによるストレスがかかり、「コロナ首」の方が出てきたのではないかと考えております。
「コロナ首」の解消法として、「コロナ首」の症状自体を解消する、「コロナ首」の根本原因である姿勢から改善する、の2つのパターンがあります。
ストレッチとして、3つご紹介しましたが、これを毎日時間があるときに行なっていただくのが理想です。
もし時間を作れない方は、朝昼晩の3回ルールを試してみるといいでしょう。
急性の首の痛みの場合は、こちらをご覧ください。